|
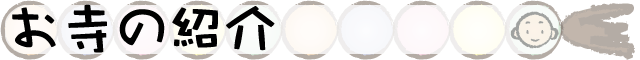
川俣:乙訓寺(おとくにでら)は栄枯盛衰をくり返しているお寺でございます。
「乙訓」というのは、この地域、乙訓地方から来ております。
郡名寺院(※1)といいまして、
地域の名前がついているお寺ですので非常に古うございます。
創建当時の資料は応仁の乱などの戦火に巻き込まれたので現存しておりませんが、
徳川綱吉公の時代に再建された時に再編された自伝によると聖徳太子の建立だと
いうことですので、だいだい1400年くらいの歴史がございます。
古うございますのでいろいろな歴史的事件に関わっておりまして、
一番有名なところですと、映画『陰陽師』で有名な怨霊でもある
早良親王(※2)の失脚された事件ですね。
このお寺に幽閉されたとのことですので、映画の舞台になっております。
その後、真言宗の開祖であられます弘法大師空海さま(以降お大師さまと呼称)
が当山の別当(※3)に任命されまして、1年近く勤めていらっしゃいました。
その間に、天台宗の最澄さまが真言密教の教えを請うために当山に一泊され、
夜を明かして語りあわれたということが、資料としてたくさん残っております。
そのように、日本史的にも仏教史的にも非常に分岐点となるところに関わって
いるお寺でございます。
(※1) 郡名寺院 (ぐんみょうじいん)―地名から名付けられた寺
乙訓という地名は諸説のうち、葛野(かどの)郡から分離して
新しく郡を作るとき、葛野を「兄国」とし、
新しい郡を「弟国」(乙訓)としたと見るのが妥当。
『日本書紀』によると、第26代継体天皇は河内で即位され、518年3月、
都を弟国に移された。乙訓寺は当時の宮跡として有力視されている。
(※2) 早良親王(さわらしんのう)―光仁天皇の皇子。
同母兄桓武天皇の即位とともに皇太子となる。
785年藤原種断暗殺事件に連座して、乙訓寺に幽閉された。
その後、一切の飲食を拒み無実を訴え、淡路に配流される途中に死亡。
怨霊として祟ったとされ、800年崇道天皇の尊号が追贈された。
(※3) 別当―大寺で寺務を統括する長官に相当する僧職

乙訓寺本堂
|
川俣:また、お寺の特徴としては牡丹ですね。長谷寺の流れを汲んでいますので、
その流れで牡丹園をさせていただいております。
中山:牡丹は境内には何株くらい植えられているんですか?
川俣:だいたい2000株近くございます。
中山:牡丹園の歴史は何年くらいになるんですか?
川俣:だいたい40年くらいと聞いております。
昭和9年の室戸台風で非常に境内が荒れまして。
その時、私がお名前を頂戴しております平岡全教海雲和尚(※4)が長谷寺で
猊下をされてまして、その時に2株の牡丹を私の祖父に渡したんです。
台風で荒れた境内地を整備する際に、本尊である十一面観世音菩薩さまの
供花でもあるし、お参りの方の心の安らぎにもなるだろうから
牡丹を育ててみないか、というのが始まりでございます。
ただ、本格的にこれほど境内を整備したのはうちの父の代で、
聞くところによると、昭和40年から45〜6年の間に整備していったという
ことですので、私が生まれたのとだいたい同じくらいの歴史があるらしいん
です。
(※4) 平岡全教海雲和尚―総本山長谷寺第六十八世化主
川俣海雲師の大叔父さま
|

乙訓寺と牡丹
|
中山:お大師さまの住持されていたお寺ということで、お大師さまゆかりのものなど、
残っていたりするんですか?
川俣:この地域は戦国時代に戦火に巻き込まれましたが、
菩提樹がお大師さまの御手植えと伝わっております。
それから、客殿の前にある蜜柑の木が、『性霊集』(※5)にございます
嵯峨天皇に献上された蜜柑の何百代目かの子孫だと伝わっております。
(※5) 『性霊集』―お大師さまの詩、上表文、願文などを
弟子の真済(しんぜい)が集成したもの
『性霊集』によれば、 お大師さまは唐から持ち帰った蜜柑を乙訓寺で
栽培されたそう。
またお大師さまは『沙門空海言さく。乙訓寺に数株の柑橘の樹あり。
例により摘み取り、来らしむ。・・・」としたため、
「・・・よじ摘んで持てわが天子に献ず」の詩を添えて、
嵯峨天皇に献上されたと記されている

蜜柑の木

川俣:子どもの頃から本山に住んでいて周りはお坊さんだらけでしたので、
当然僧侶になるものだと思って育ってまいりました。
ただ思春期の高校生くらいの時に、一度違う世界に行ってみたいと、
いろんな道を探ったことがあるんです。
理想的なことを言って違うところを目指したのですが、
自分の理想を実現するには他の道ではなく、
僧侶の道が実は一番近いのではないかということに気づきまして。
それで軌道修正して、僧侶の道に進もうと考えました。
|

牡丹園
|
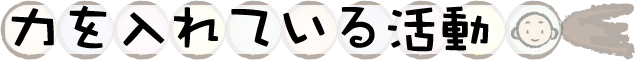
中山:普段お寺を運営されていく上で、力を入れている活動、得意分野等ございますか?
川俣:正直な話、このお寺を維持していくのがいっぱいいっぱいのところはあるんです。
このお寺はもともと檀家寺ではございませんでして、
檀家さんも信者さんも全くいなかったんです。
なので、ここはもともと、経済的に全く安定していなかったんです。
小作で食べてきたお寺なんですが、それが戦後、農地解放で全部なくなって
しまいましたんで、うちの祖父の代は勤めに出ていました。
今信者さんや檀家さんのような形で来ていただいている方は、
ほとんどが故郷を離れて分家の立場として来られてるんです。
先祖供養などするのが自分の代で初めてという、場所は田舎なんですけれども、
信者さんの形式がとても都会的なんです。土地にも縁故はないですし、
親から引き継いでいる先祖さんもないという形の方が非常に多ございます。
教化活動に力を入れていかないと、まったくお寺に寄りついてもらえないような
状態ですんで。
思い出したように何年かに一度法事をお願いしてくる、
もうほとんど顔も覚えてないような状態の方が多かったわけですよ。
それができるだけ、春夏秋冬、機に応じて仏さまに親しんでいただくということ
が、イコールお寺の維持、発展でもありますんでね。
そういうところにできるだけ重点を置いてやっていこうと考えて
今いろんなことをしておるわけですね。
ですんで、牡丹は確かにお寺に寄っていただく等いろいろなきっかけにはなると
思いますけど、ある程度安定させていかないといけませんのでね。
その二本で、さしていただいておるわけでございます。
ですんで普通のお寺さんでしたら当たり前かもしれませんけども、
お彼岸をしたり、お寺に来てもろうてお経あげたりとか、
そういうようなことで、すこしでもお寺に顔出してもらっています。
中山:なるほど。年間の寺行事といいますか、そういったこともしていただいて。
川俣:そうですね。今は両彼岸とお盆と、お砂踏みという行事をしています。
宗教的な行事を、これからも少しずつ増やしていかなあかんなと思っている
ところでございます。
中山:ちなみに、牡丹のシーズンはどれくらいの方がいらっしゃるんですか?
川俣:今はどこでも厳しくなっていると思うんですけども、ピーク時には2週間で
3万人を超える時期もありました。1日最大で6000人くらいですね。
|

川俣:お檀家さんに現実的な話をする時が一番つらいですね。
お寺の維持のためには言うべきことは言わないといけませんのでね。
お葬式等で、大事な人を亡くして泣いていらっしゃる方に、
費用等のことを話す時とか。かといってうやむやにしても後でトラブルに
なることも多いですんで。
お金の話以外にも、お墓などもきちんとした形でルールを守っていただかないと
いけませんし。言うべき事を言わないと維持していけませんのでね。
ですんで、できるだけ上から物を言うようなことは避けるようには
してるんですけれども、言うべき時には言わないといけませんので、
檀家さんと言い合いになったりってとこもありますね。
そういう、やらざるを得ない現実的な話が、つらいと言えばつらいですね。
中山:そうですね。私たちは宗教者であると同時に一寺院の代表役員というか
経営者というか。
川俣:実際、お寺をつぶすわけにはいきませんのでね。
中山:運営していかないと。
川俣:これが仏具商売でしたら当たり前のように言えることでも、
やはり衣を着ていると言いにくいことがあるんでね。
それと並行して癒しの事とか理想的な事も言っていかないといけないんで。
両方大事な仕事なんですけども、そこにギャップがあるところがつらいですね。
やっていてよかったと思えることは、乙訓寺でお葬式してもらえ
よかったと言われた時ですね。お葬式の中での諷誦文(※6)や、
法話や相談にのるような形でお話したりすることで、
ある程度気持ちの整理がついたとか、悲しいけれども受け入れることが
できたという言葉が聞けた時は、非常に充実感を感じますね。
(※6) 諷誦文(ふじゅもん)―葬儀の際、故人の追善のために導師が読み上げる文
川俣師は故人の生前の行いを讃えるために、その度ご葬家の皆さんに
喜んで貰えるよう力をいれて作成しているそう
|

インタビューの風景 |
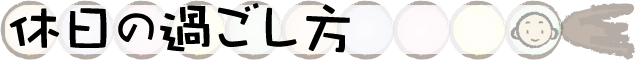
川俣:父親が今本山でお役をもらっておりますし、弟も奈良で岡寺をまかされて
おりまして、当山の交代の者が誰もいませんので、
ここ2、3年はまともな休みというのがない状態です。
最後にとった休みが、2009年の9月に、阪神のピッチャーの岩田選手が、
中日ドラゴンズ相手に完封した時が最後かな。
お嫁さんと二人で甲子園に野球を見に行ったそれが最後。
それから今まで一日も休みがないですね。
中山:無休で。
川俣:はい、無休ですね(笑)
中山:大変ですね。体力的なことも大変だと思うんですけど、
仕事の疲れをリフレッシュしたりするようなのは。
川俣:仕事自体が体力を酷使するとか徹夜で何かするとかはないんですけども、
オンとオフがないんで、それに慣れるまでが大変でした。
実際、お葬式やいろんな依頼は24時間関係なく、
8時でも9時でも電話がかかってきます。
それでなかなか息休まらないというか、仕事が延々続くような感覚に陥るんです。
それがしんどいと言えばしんどいですね。激務ということはないので、
特に体力的にきついということはないんですけども。
中山:趣味や気分転換になることはないんですか?
川俣:どうしても家を出られませんので、映画や海外ドラマを自宅で観ること
くらいかな?
中山:どうしても家の中でやれることになるわけですね。
川俣:あと、うちは犬を飼ってますんで、夫婦で犬の散歩をしたり。
まれに遅くまでやってる喫茶店に行ってコーヒーを飲んで帰ってくるとか。
その程度ですね。
|
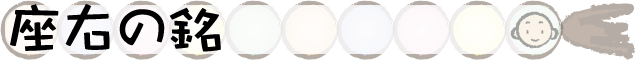
川俣:「明日の私はスーパーマン」という言葉です。
私はなんでもかんでも先送りにする方なんです。
今日できないことはやっぱり明日もできないんでね。
それがいつかできるということになると、先々の自分はスーパーマンなのかと。
中山:楽観的なものではなく、自戒の意味での「明日の私はスーパーマン」と。
川俣:そうですね。明日の私がスーパーマンになれるわけがないだろうと。
今日できないことは明日も出来ないんだから、今日できることは今日する、
としないと。
住職となるといろんな仕事があるので、先送りするとたまっていく
一方ですんでね。自戒を込めて。
中山:すごく身につまされる自戒の言葉ですね。ありがとうございました。
|

中山委員長と川俣僧正
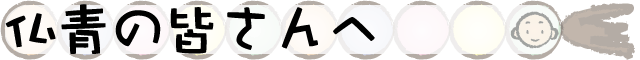
川俣:非常に恐縮ですけれども、今とても難しい時代に入っていますんで、
宗教に対する見方も厳しくなってきてます。
その中で仏青のみなさんは教化活動など、宗派のためになることを、
忙しい中時間を見つけてなさっていますんで、お疲れさまでございます、
ありがとうございます、と感謝しております。
川俣海雲師、貴重なお話をありがとうございました。
乙訓寺は真言宗豊山派が誇る古刹ですので、歴史や文化財の仏像についてなど
ここでは書ききれないほどのお話があります。
気になる方はぜひ乙訓寺HP(http://www.eonet.ne.jp/~otokunidera/)を
ご覧ください。
インタビュアー:中山和光
カメラ撮影:石原了文(高野山真言宗)
文:加藤孝綾
校正:藤田妙和
|