 |
 |

| 【豊山仏青機関紙 豊友第142号】 平成23年12月1日発行 発行者:豊山派仏教青年会 真言宗豊山派宗務総合庁舎内 (直通)TEL・FAX03-5940-0585 発行人:橋將雄 編 集:豊友出版部 |
||||||
|
栃木県仏教青年会 全国結集実行委員長 田戸 大智 ○第39回 豊山仏青全国結集大会に参加して |
||||||
| . 第39回 豊山仏青全国結集 栃木県仏教青年会 全国結集実行委員会 実行委員長 田戸 大智 |
||||||
 |
||||||
「第三十九回 豊山仏青全国結集」に際しましては、真言宗豊山派管長・総本山長谷寺化主、更には豊山仏青の初代理事長でいらっしゃいました小野塚幾澄猊下、法要の大導師をお務め頂きました大本山護国寺貫首 岡本永司台下、宗務総長 川田聖戍台下をはじめとする宗派諸大徳様に、大変ご多用のところ、ご臨席を賜り誠にありがとうございました。また、ご参加頂きました一〇九名の豊山仏青会員各位にも、厚く御礼申し上げます。 今回の結集では、「いのちを見つめ直す」というテーマのもと、震災に関連する諸問題を考える研修会とさせて頂きました。豊山仏青においても、千響様をはじめ有志の方々が被災地に赴き、様々な支援活動を行っていると仄聞しております。支援活動には様々な形があるかと思いますが、大和証券(株)の石田佳宏様、(財)メンタルケア協会の精神対話士・輿石邦彦様のお二人によるご講演が、参加者各位の今後の諸活動に大いに反映されることを期待しております。 また、護国寺観音堂では、本尊如意輪観世音菩薩とともに、豊山仏青の送り大師像にもご出仕頂き、「震災追悼・復興祈願法要」を厳修させて頂きました。今後、被災地でも、送り大師像を本尊とした同様の法要が営まれることになれば幸甚に存じます。 実行委員会と致しましては、本結集が豊山仏青における今後の支援活動の礎となることを強く願っております。 最後になりましたが、会場使用をご快諾頂いた宗派宗務所及び大本山護国寺様、並びに関係各位の皆様に御礼申し上げまして、実行委員会を代表してのご挨拶とさせて頂きます。 |
||||||
  |
||||||
| →もくじへ |
||||||
第39回 豊山仏青全国結集大会に参加して 千葉一号 宝藏寺 櫛田 良成 |
||||||
|
|
||||||
| →もくじへ |
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
||||||
去る11月8日・9日に、第32回全真言宗青年連盟結集宮島大会が開催された。 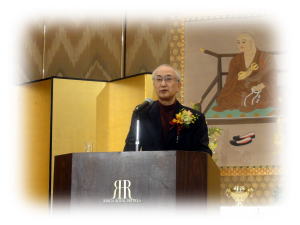 一日目は、市内のリーガロイヤルホテル広島で、国際日本文化研究センター教授で仏教学者の末木文美士先生による講演が行われた。それに先立ち、紺紙に金泥で書かれた十八本山種子掛軸開眼法要が厳修された。会場に並べられた十八幅の御軸は、種智院大学教授児玉義隆先生の筆によるもので、大変立派なものであった。また、僧侶と業者の交流をはかる新しい試みとして全青連フェスタが開催された。 二日目は、3月11日に起きた東日本大震災の慰霊を行うべく、晩秋の風が吹く瀬戸内海に浮かぶ宮島に、全国から真言宗各派の青年僧侶たちが集まった。お大師さまの事跡を伝えるこの地に現れた僧侶の列は、雅楽の音色と共に厳島神社を目指す。参道を伝い、黙然として歩む姿は、華やかさのなかに厳粛さを漂わせていた。  そして、神域とされる厳島神社の拝殿で厳修された千僧法要は、圧巻のひと言であった。朱塗の柱の下には、大海のごとき僧侶たち。被災で亡くなられた精霊、また、避難生活のなかで復興へ向けて努力する方々のために、会派を越えて祈りをささげた。 その後、弥山の麓に伽藍を構える真言宗御室派の大本山大聖院に向かった。弥山は、霊峰の名にふさわしく、霊気漂う深遠なる場所であった。大聖院は、大同元年(806年)にお大師さまが三鬼大権現を勧請し、弥山を開基して以来、1200年の歴史を有する西国の大寺院である。山頂にある弥山本堂は、当山開創の際に、お大師さまが修した求聞持満座の霊跡であり、求聞持の燈火、今に絶えざる「消えずの火」がいまも灯る。 今回自分は、はじめて広島の原爆ドームを見た。戦争と震災。ともに多くの人々に深い悲しみを与えた出来事である。一僧侶の私には、荷が重すぎる問題である。しかし、真言宗青年僧侶たちと共に考えていきたい。そんな気持ちにかられた結集であった。 |
||||||
|
||||||
|
||||||
今回は豊山派仏教青年会の事業の中でも長い歴史をもつ写仏講座担当の猪狩事業次長と写仏講座のお手伝いをしていただいている櫛田さん、南合さん、守山さん、山崎さんにお話をお伺いしてみました。 広報:本日はお忙しい中、お時間をいただきましてありがとうございます。前任の広報次長から受け継ぎましたこのコーナーも今回で第3回目となります。写仏講座は豊山仏青の事業のなかでも長い歴史がありますが仏青会員の方々にはあまり接点がないことと、今月写仏展覧会があるため取り上げてみようと思っていました。それではよろしくお願いします。 猪狩・櫛田・南合・守山・山崎:よろしくお願いします。 広報:まずは写仏講座の歴史と現在の受講者数について教えて下さい。
山崎:3月の震災の数日後にも写仏講座は開かれてお手伝いをしましたが、交通網が混乱している時期にも関わらず来ていただいた方が多くいてその時はとても感動しました。 広報:皆さんは写仏講座のお手伝いをするようになってからどのくらいになりますか。
猪狩:以前は大学時代の同級生に手伝ってもらうことが多かったですが、最近は山崎君や若い方にも手伝ってもらっています。 広報:写仏講座は主に宗務所にて開催されていますが、それ以外にも展覧会などのイベントを開いていますがそれについてお聞かせ下さい。 猪狩:二年に一回、寺院をお借りして展覧会を開いています。十年に一度の記念事業の時には銀座の画廊を借りて大々的に展覧会を開いています。展覧会以外のイベントですと鈴木執行部の時には長谷寺へ参拝旅行も行いました。 守山:写仏講座の受講者の方も毎回宗務所で写仏しているだけではなく、完成した作品を発表するという目標があると普段の講座での気合の入りかたが違ってくると思います。 南合:特に展覧会直前の受講者の気合の入り方を見ると2年に一度の展覧会にて自分の作品を多くの人に見ていただくということは大事だと感じますね。
広報:写仏講座で取り上げる仏様についてお聞かせ下さい。 守山:写経だと毎回毎回同じお経でも良いけれども、写仏講座で同じ仏様だと受講者の方が飽きてしまうので豊山仏青の写仏講座では毎回取り上げる仏様が違います。
櫛田:木下先生は取り上げた仏様について講座内で解説していますが、それだけではなく時節に合わせた話など縦横無尽に話が広がっていきます。自分ではとてもまねできないぐらいでそのバイタリティを少しわけてもらいたいぐらいです。 守山:木下先生の話を毎月聞く事が出来るのも写仏講座の魅力のひとつかもしれません。 広報:写仏をおこなっている御寺院もありますが、宗務所に行き、受講するということの魅力とはなんでしょうか。 猪狩:やはり宗務所の写仏講座を受講すると他の御寺院のお檀家さんとの出会いがあり、その方々と色々と話をすることによって人と人とのつながりができるということにあると私は思います。 広報:本日はお忙しい中ありがとうございました。 |
||||||
|
||||||
|
|
|
| 豊山仏青広報次長 塚田 宝貴 | |
ページ上部へ戻る |
|
 |